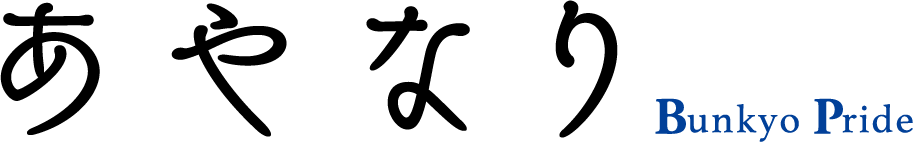鈴木 美子 先生
(文教大学付属幼稚園(越谷幼稚園)/1979年〜1981年在籍)
先進的な教育が行われていた幼稚園
入園式や誕生会などの行事の際、文教大学付属幼稚園(越谷幼稚園)でよく行っていたという人形劇。約40年前に保護者の方々が創ったという、腕の長さほどもある大きな人形を何体も愛おしそうに見せてくれた鈴木美子先生。手に人形を被せれば、自然にセリフが口をついて出てくる。保護者の有志が演じる人形劇を、子どもたちは楽しみにしていたそうだ。
「文教大学付属幼稚園は、保護者との協働が本当によくできていたと思います」と振り返る。「園外保育の補助、保護者主体のバザーや人形劇など、文教の保育は保護者の方々に支えられていました。文教ではすでに40年前から『保育参加』を行なっていたのです。保育の様子を見る『保育参観』は、ともすると自分の子どもだけを目で追いがちですが、『保育参加』は保護者が保育補助の立場で日常の保育に参加し、子どもたちの成長や保育の理解を深めます。今でこそ盛んにその重要性が取り上げられるようになりましたが、文教の指導計画には、当時からしっかりと位置付けられていました」
その話しぶりから、若手の教員だった先生にとって、文教大学付属幼稚園での3年間がいかに大きな意味をもっていたかがわかる。

一人ひとりの子どもの歩みに寄り添って
「この幼稚園は、子どもが自ら興味や関心をもってかかわることができる豊かな環境が用意されていました」
その例を伺うと、園庭には2つの砂場と築山やアスレチック、流れる川に雑草園、畑と飼育小屋(小鳥、鶏、ウサギ)などがあり、子どもは土や水、虫や小動物といった身近な自然に心ゆくまでかかわって遊びを生み出していたのだと言う。雨上がりに葉の上を這うかたつむりをじっと見つめる子ども、水滴をまとってキラキラ光る蜘蛛の巣をいろんな方向から見ようとする子ども、お尻にあて布で補強したマイクロパンツ一丁で築山を目指す子どもたちなど、先生方の温かな目に見守られながら、さまざまな体験を積んでいく子どもたちの様子がまざまざと浮かび上がる。
子どもたち一人ひとりを丁寧に受け止めることは、専門家であっても難しいはず。しかし、子どもの新たな面を見出す喜びがそれを遥かに上回っていたことを、話をする先生の笑顔が証明する。

仕事の合間の息抜きは、おいしいもの探し
幼稚園の先生から教育委員会へ、さらに聾学校の幼児部での経験を経て、今は東京福祉大学短期大学部こども学科の教員として、保育に関わろうとする学生たちに教える立場だ。
忙しい毎日ではあるものの、合間を縫っておいしいものを探しに出かけたりしている。現在住まいがある高崎市は、東日本一の梅の生産量を誇る街。「群馬は『白加賀』という品種が有名。自然落下した完熟梅を7 %の塩分だけで漬け込む梅干しは、自然の旨みが凝縮しています。お茶請けに小梅『織姫』の梅干しとカリカリ梅を食べ始めると止まらなくなります。花の季節に出かけると梅の香りがふわっと漂って、とても気持ちがいいですよ」